僕はサル。
サルが彼女の元を永遠に去るまでの、さる恋のおはなし。
ナルな文章にならないように気をつけようと思うけど・・自信ないな。
これは僕の初恋についてのはなしです。
Ⅰ

固いフローリングの上の毛布に包まって僕は目を覚ました。
街の喧騒と目の前を走る高速道路から伝わる微妙な振動でまともに寝た気がしなかった。
壁にもたれかかると、家具どころか、まだベッドも敷布団もない、がらんとした部屋をしばらく見回して、
自分がどこにいるかをだんだんと認識した。
2月8日、今日は一人暮らし最初の朝だ。
僕は、ベランダ一杯に広がった高速道路の防音壁を見ながら、煙草に火をつける。
今から約15年前のこと、僕は16歳だった。
高校は半年で中退した。
理由は簡単に言えばイジめられたからで、ややこしく言えば、感性が過敏過ぎたのだと思う。
すべてのことに過剰に期待し、勝手に裏切られ、よせば良いのにまた期待した。
ほんの些細なことに傷つき、気に病み、それでもそれを無視できなかった。
僕はとても疲れていた。
10月に高校を辞め、しばらく自宅に引きこもっていた僕だが、狭い田舎でのこと。
僕の状況は近所に知れ渡っているはずだった。
見栄坊の僕は、(○○さん家の長男、高校辞めて引きこもってるらしいわよ)と云われているであろう状況に耐えられなかった。
とにかく地元を出て働くことにし、実家から車で2時間程度の県庁所在地の市で一人暮らしを始めたのだった。
ベッドは翌日には届き、僕はアルバイト情報誌片手におっかなびっくり仕事探しを始めた。
それまで、まともなバイト経験はない。
当時の僕はビジュアル系バンドにかぶれていたりした影響で金髪だった。
コンビニに面接に行き、「その髪型では採用できない」と云われ、一旦帰りかけたが、
(こんなことじゃ生きていけない)と思い直して引き返し「髪黒くするのでお願いします」と頼んだこともあった。
店長は戻ってきた僕をみて、蔑むように「そういう問題じゃないから」と言った。
僕は、(結局髪の問題じゃねぇんじゃねぇか!!)と思い、腹が立ったし、心の底から惨めな気分になった。
僕は涙目になりそうになるのを必死にこらえながら店を出た。
十代は誇り高い。なんであんなに誇り高いんだろう。
Ⅱ

コンビニでの面接の一件で心がぽっきり折れた僕は、面接にいくのが怖くなった。
親からの仕送りで、何とか食ってはいけるし、地元を離れるという目的は達成できているので、僕の仕事探しは緩慢になった。
それでなくても僕はとても疲れていたのだ。
無為な2月も終わりに近づいたある日、朝方、非通知着信で携帯が鳴った。
今なら非通知の電話には出ないだろうが、昼夜逆転で毎日なすこともない僕は、何気なく電話に出た。
電話の向こうは酔っ払った女の子だった。
「青森のユカ」と名乗ったその女の子は、友達と適当な電話番号に電話をかけるという遊びをしていて、たまたま僕に繋がったと云う。
実際、当時そういう遊びはなくもなかったが、「青森」のユカに訛りはなく、その声には聞き覚えがあった。
その日はお互いの年齢(ユカは17歳と言った)とか境遇を話し電話を切った。具体的に何を話したかは良く覚えていないが、通話時間は1時間を越えていたと思う。
その日から、週に何度か「ユカ」から電話が来るようになった。
電話が来るのは決まって深夜で、いつしか僕も「ユカ」からの連絡を待つようになっていた。
僕は一人でいることを苦にせず、むしろ一人でいることが好きなほうなのだが、流石に見知らぬ街に一人ぼっちで、
毎日、一言も話さない日が続くと自分が存在していないかのような気にもなってくる。
また「ユカ」が「見知らぬ同年代の女の子」であることも僕にとっては気楽で、性的にも何らかの意味を持っていた。
だからこそ僕は言うのを迷っていた。
つまり、「ユカ」が「沙希(サキ)」であることをだ。
沙希は僕の中学校のときの同級生である。
最初の電話のときにも、ほぼ気づいていたが、2回目の電話では確信に変わっていた。
沙希の「青森のユカ」の設定はあまく、ちょっと突っ込んだ質問をするとしどろもどろになっていたし、
むしろそうなることで、自分の存在を匂わせていたのかも知れない。
4回目の電話で僕は言った。
「もういいんじゃない?」
「いいってなにが?」
「だから・・その設定」
「ふふふふ・・・やっぱり、ばれてた?」
真夜中の狭いワンルームで久しぶりに声を立てて笑った。
沙希は奇特な子で、中学のときから僕を好きだと云ってくれていた。
一度は告白もしてくれたし、卒業式の日には学生服のボタンをほしいと云ってくれた。
ただ僕は女の子に人並み以上の興味を持ちながらも(だからこそかも知れないが)、
女の子と付き合ったり、そんな風なことになるのが無性に恥ずかしかった。
結果、僕は彼女から逃げ回り、廊下の向こうから彼女が来ると、用もない教室に緊急避難するという過剰反応ぶりだった。
そのくせ僕は沙希が好きだった。
いわば僕は彼女に冷たい対応を取っていたわけだが、それでも彼女は電話をくれたのである。
自分に何らかの価値を認めてくれる人がいたような気がして、安心感が僕を屈託なく笑わせた。
ただ、ひとしきり笑って、笑いおさめてから「沙希」として語り始めた彼女の近況は意外なものだった。
成績優秀だった沙希は県外の全寮制の高校に入学したのだが、校風が合わず、休学し実家に戻っていると言った。
そんな状況から、最初の電話のときも自暴自棄な気分になりビールを飲んで酔っ払った状態で電話をかけてきたわけだった。
僕は高校をドロップアウトし、彼女は高校をドロップアウトしかけていたわけだが、二人の境遇が似ているとは思わなかった。
僕は元々、学校や社会に適合しにくい人間だが、彼女はそういうタイプではなく、多少頑固なところはあっても、必要充分なだけの協調性を持っている。
僕はなるべくして、彼女は何かの間違いで似たような場所にいた。
似ているところがあるとすれば、二人ともとても疲れていた事と、時間はたっぷりあることで、
数日後に彼女が僕の家を訪ねてくることを約束し、「沙希」との初めての電話は終わった。
Ⅲ

まだとても寒い日だった。
彼女は「女友達の家に行く」と親に嘘をつき、僕のマンションを訪ねて来ることになっていた。
彼女からの「駅についた」のメールを見ると、僕はダウンを羽織って部屋を出る。
途中まで行くと、大きな国道の反対側で信号待ちしている彼女を見つけ、彼女もすぐにこちらに気づいた。
信号は長かった。なんだか間抜けな距離が二人の間に横たわっている。
お互いに存在を認識しながら、何とも出来ず、変にはにかんで、視線を逸らしたり合わせたり、また慌てて逸らしたりした。
永遠にこのままなんじゃないかと思った。
永遠があっけなく終わって信号が変わると、二人は横断歩道の中央で再会を果たした。
僕は彼女と一緒に、彼女がもと来た駅前に引き返すと、酒屋でワインを買った。
「ユカは酒好きだから」と言うと、彼女は僕をちょっと小突いて笑った。
疑われるかも知れないが、なにか予感があったというわけじゃない。
「今日は絶対決めてやる」とか、そんなのもなかった。
むしろそういう想像をすることを恐れていたといえるかも知れない。
だけど、ワインを苦労して開けると、それをろくに飲むこともなく、僕らは抱き合っていた。
彼女の唇は恐ろしく甘く、この世に存在するどんな果実よりジューシーだった。
唇を合わせる瞬間の記憶はなくて、気づいたらキスは始まっていた。
舌が僕の中に入ってきて、僕はかつてない感覚とともに夢中で応対した。
僕は童貞だった。
何度か失敗しながらも、僕はなんとか彼女とひとつになった。
彼女を駅まで送ると、僕は虚脱感を伴う安心感とともにマンションまでの家路を歩いた。
自分を少なくとも一度でも受け入れてくれた人がいるという安心感は、永久に使いまわし可能な充電池のように思えた。
女性諸君、男の子ってのは初めてのとき、そんなことを思ったりするものなんです。
Ⅳ

遅々として進まない僕の仕事探しの状況を察した親は、親戚に手を回し、僕は親戚のコネで家具の運搬の仕事をすることになった。
指定された現場、ショールームやホテル等に出向き、トラックから家具を運び出したり、逆にトラックに家具を積み込んだりする。
純然たる肉体労働だが、実際、当時の僕に出来る仕事はこれくらいだっただろう。
僕にとって、仕事以上に困難だったのは、毎回変わる仕事現場までたどり着くことだった。
田舎者の僕にとって、複雑に入り組んだ電車の路線は理解が難しかったし、最寄駅についたところで、そこから現場まで、
道を間違えずにたどり着けることの方が少なかった。
ほんの50m先の目的地が分からず、やむを得ずタクシーを捕まえると、「兄ちゃん、目の前やがな」と呆れられたこともあった。
プライドがずたずたになるような日々を送りながらも、僕からは沙希に連絡を取らなかった。
理由はよく分からないが、「付き合う」という経験をしたことがなかった僕は、どれくらいの頻度で連絡を取り合うものか等も良くわかっていなかったのかも知れない。
生来の物臭や自分勝手さの影響もあるだろうし、仕事でくたくたになっているということもある。
さらに白状すれば、「連絡なんて取らなくても、彼女は僕のことを好きでいてくれる」と思っていたのだ。
春が過ぎ、夏も終わりに近づいた。
その間、彼女は物臭な僕にも懲りず連絡をくれたり、会いに来てくれたりした。
なかなか連絡が取れず、約束も出来ない僕をマンションの廊下や屋上で帰るまで待っていてくれた事もあった。
まともにデートなんてしたことはなく、会うのはいつも僕の部屋で、やる事といったらあれだけだ。
彼女は女の子を女の子たらしめている要素を豊富に備えていた。
白くやわらかい肌、さらさらの長い髪、推定Dカップの胸、フェミニンなのにさっぱりしたファッション、猛烈に良い匂い。
歯列矯正の金具まで可愛いと思ったのは、病のせいに違いないが、客観的に見ても彼女は美少女と云える存在だったと思う。
僕はサルだった。
彼女を駅に迎えにいく。
彼女が改札から出てくると、もう僕は勃起している。
駅からマンションまで歩いているときも歩くのが難しいくらい勃起したまんまだし、部屋に入ったらもう雑談に応じる余裕なんてない。
十代男子は不条理で切ない生理を抱えているのだ。
かといっていざ行為に移ろうとすると、なんだかよく分からない屈託から、萎んでしまったりもする。
十代男子の生理は不条理な上に不器用なのだ。
9月の始め頃、それまで週に一度は来ていた彼女からの連絡がぱったり途絶えた。
Ⅴ

彼女から連絡が途絶えて約2週間経った9月半ば、僕は自分の胸の奥の不安に気づかないフリをしながら沙希にメールを打った。
「久しぶり~ また時間あったら遊ぼ~♪」
しばらくして届いた返信メールを見て僕は世にも奇妙な顔をしていたと思う。
「もう会わないから」
返信の内容が意外だったわけではない。その返信メールを見て、自分の中に沸き起こった感情が解せなかったのだ。
僕は恐ろしいほどの不安に襲われた。
最も近いのは、人ごみで親を見失い迷子になったときの心境だ。
だけど僕はもう16。そんな感情を味わわなければならないハズはない。
そもそも僕は人に依存するタイプでもなく、むしろ一人で居ることが好きなタイプだ。
僕は暗い部屋でタオルケットを頭から被り、(なんかおかしい、そんなハズない)と何度も自分に言い聞かせた。
だけど、そのうち僕は認めざるを得なくなる。
人にはどうしてもその人じゃなきゃならないという存在がいるらしい。
僕にとって彼女がそうで、そしてそう知った瞬間彼女は去っていく。
「かけがえがない」は痛みと共にしか知ることが出来ないのだ。
Ⅵ

それでも僕はどうやら少し眠ったらしい。
ただ、僕の淡い期待に反して、翌朝も「痛み」は消えていなかった。
僕は8月頃から、バイトの傍ら、親の薦めで大学検定取得の為の予備校に通い始めていた。
今日はその予備校の日だったが、唯でさえサボりがちな予備校。
こんな日くらいサボっても、僕にとって何の差し障りもないのだが、「痛み」が僕に一人の部屋にいることを許さなかった。
誰かに無性に会いたくて、こんな感情も初めてのことだった。
原付を走らせて予備校に向かったが、到着すると授業が始まるまでにはまだ少し時間があった。
校舎脇のベンチで携帯をいじっていると、同じく大検取得のため、予備校に通っている2つ年上の男子生徒がやってきた。
彼とは時々言葉を交わす程度で特に仲が良いわけでもなかったが、その日は彼の顔を見て少しほっとした。
人生では時々、良く分からない歯車がかみ合ったりするものだと思う。
しばらく雑談した後、彼は嬉しそうに話し始めた。
「今日な、彼女とのペアリング買いに行くんだよ。あやがさ、あ、あやって彼女な。欲しいって言うからさ。
石はオパールが良いって言うんだけどさ・・いまいちピントくるデザインが・・」
僕はしばらく平静を装って相槌を打っていたが、長くは続かなかった。
つまりまぁ、具体的に言うと号泣した。
僕自身も自分の号泣に驚いたが、彼も、普段あまり感情を表に表さない僕の号泣に驚いたらしく、親身に事情を聞いてくれた。
いずれまた彼について語るときがくるかも知れないが、彼は良いヤツなのだ。
とても良いヤツと言っても差し支えない。
これ以降、彼と僕とは親友といっていい存在となった。
数時間後、僕と彼は地下にあるジャズバーでベロベロに酔っ払っていた。
彼はこの街の出身で遊びなれたところもあったので、行き着けのジャズバーに傷心の僕を連れて行ってくれたのだ。
彼はろれつの回らない口調で言う。
「なお(僕だ)がさぁ、そこまで彼女を好きなら、別れたくないって言うべきだ。なにも彼女の言い分をそのまま受け入れる必要ない。
少なくともなお自身の気持ちを伝えるべきだよ。それでダメなら仕方ないけど。」
ソファに腰掛けていても、僕の世界はぐるぐる回っていた。
バイキングじゃないが、「なんて日だ!!」って言いたい。
昨日から今日にかけ、僕はなんてたくさんの感情を知ったことだろう。
人には、その人じゃなきゃならないという存在があることを知り、人前で号泣してしまう自分を知り、号泣するのが意外に気持ちいいことを知り、自分をさらけ出せば手を差し伸べてくれる人がいることを知り、例え相手が自分を拒否したとしても自分の想いを伝えるという選択肢があることを知った。
僕は彼女に電話をかけた。
彼女は驚いていた。
とても驚いていた。
Ⅶ
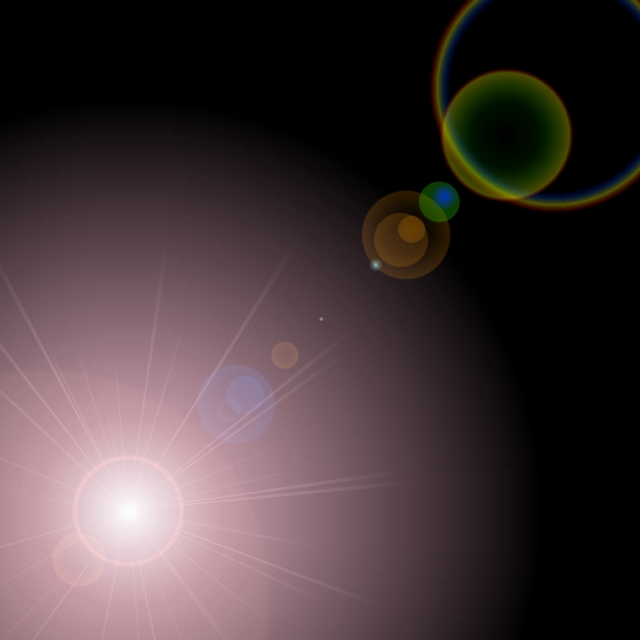
僕たちは復縁した。
そしてその後、2年に渡り、くっついたり離れたりを繰り返した。
その間、彼女は別の高校に編入し、僕は大検を取得している。
僕の彼女に対する想いは紛れもなかった。
だけど、だからといって僕が素晴らしい人間になれるわけでもないし、
紛れもなく彼女が好きであるという激しい感情は、「彼氏」「彼女」というある意味で日常性を必要とする関係には実は不向きだったりするのだ。
つまり、人が一緒にいれば、ご飯も食べるし、排泄もする。
買い物にも行くし、愚痴も言う、そういう事務手続きのような日常に、過剰な好意は必要ないどころか邪魔だったりする。
好きだから復縁するが、大きすぎる好きの感情を抱えたまま、彼氏、彼女という日常を送れず別れる。
そんなことの繰り返しだったように思う。
本来優秀な彼女は編入後の高校を卒業するとともに山梨県の大学に行くことになった。
僕は関西に住んでいたので、山梨県なんてどうやって行くのかもすぐに思いつかない遥かな土地だ。
一年ほど連絡が途絶えた。
どうやら、今回は本当に二人の関係も終わったらしいと思った頃、沙希から電話が来た。
僕は沙希に遅れること1年、東京の大学に行くために、16歳から約3年間住んだ部屋を引き払う準備をしていた。
突然の連絡に驚きながら電話に出ると、懐かしい声がした。
「ユカだよ」
僕はやっぱり彼女を愛していることを思い知らされながら言う。
「今日は酔ってないね」
「友達と適当な電話番号に電話する遊びしてるの」
「以前にもそういう人がいたよ」
「青森に住んでるの」
「知ってるよ。青森の地名ひとつも知らないことも」
夕暮れが濃くなった部屋に懐かしい笑い声が響いた。
「なお、あの部屋引き払うんだってね。大野君に聞いたよ。あの部屋がなくなるなんて不思議な感じ」
大野は中学時代の同級生で二人の共通の友人だ。
僕は沙希もこの部屋にそれなりに思い入れを持っている事を少し不思議に感じた。
「うん、明後日には鍵返す。もうベッドも持ってちゃった。」
「そっかぁ。なんかとっても不思議。」
沙希は繰り返した。
今思えば、沙希にはサプライズ好きなところがあったらしい。
沙希との電話の次の日、僕は一人暮らし最初の日と同じく、固いフローリングの上の毛布に包まって目を覚ました。
壁にもたれて煙草をふかしながら、携帯を手に取ると、沙希からのメールが何通も届いていることに気づく。
『寒いよ~』
『ここは高いな~』
『少し晴れてきた』
『寝坊すけさんはまだ寝てるかなぁ』
『もう帰ろっかなぁ』
心臓が高鳴り、眩暈がした。
僕は顔も洗わず、はやる気持ちでエレベーターでマンションの屋上に向かった。
彼女はいつかと同じように、風のビュービュー吹く屋上でミルクティーを手に、膝に顔を埋めて座っていた。
僕はその場にへたりこんでしまった。
彼女はゆっくりと顔を上げると「来ちゃった」と笑った。
彼女は昨夜、僕との電話を終えてすぐ、夜行バスで山梨から会いに来てくれたのだ。
その日僕たちはもしかしたら初めてかも知れないデートらしいデートをした。
これまで彼氏らしいことをしてあげられなかった罪滅ぼしみたいな気持ちもあったのかも知れない。
商店街を歩き、洋服や雑貨を見て周り、カフェでお茶をした。
彼女の話に耳を傾け、彼女の心に目を向けた。
思えば僕はこれまで、自分の感情を彼女に押し付けてばかりだったのかも知れない。
不思議なくらいあっという間に時間が過ぎた。
夕方になると3月の風はとても冷たい。
僕たちは「再会の日」の酒屋でワインを買うと部屋に戻った。
二人は薄暗い部屋で壁にもたれて出前のピザを食べ、ワインを飲み、車の行き過ぎる音を聞きながらキスをした。
どこに向かっているのか分からない不思議なキスだった。
固い床の上で、僕たちは約1年ぶりに結ばれた。
かなり飲んだし、疲れてもいたらしく彼女はすぐに眠ってしまう。
僕は彼女の髪を撫でながら、空が白むのを見ていた。
翌朝早く、彼女はバスに乗って山梨に帰って行った。
昨夜、結局一睡も出来なかった僕は、あんまりにも眠くて、彼女とのお別れの際にも、あまり感情も実感も湧かなかった。
バス乗り場まで彼女を送っていった僕は、部屋に戻ってそのまま毛布に倒れこむ。
僕も今日の夜にはこの部屋を出なければならない。
僕は何にも考えずに眠った。
Ⅷ
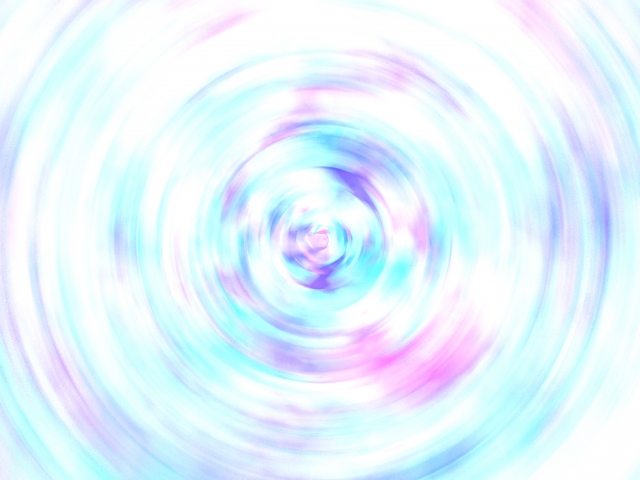
どこかでクラクションの音がして、僕は目を覚ます。
あたりはもう薄暗かった。
僕たちは眠って起きて、眠って起きての繰り返しみたいだ。
いつもの様に壁にもたれて煙草をふかし、僕は昨日の残骸を見つめた。
ワインの空き瓶、食べ残しのピザ、丸められたティッシュペーパー、昨日買った洋服の紙袋、彼女の忘れてったタオル。
僕は間抜けなくらい泣いていた。
彼女とはもう会えないんだと確信していた。
彼女は普通に生きて、普通に幸せになれる人だった。
そして僕はそれを彼女に与える事ができなかった。
そういう事だったんだと思う。僕の確信は。
さっき別れたばかりだったけど、僕たちは最も遠くにいた。
決まった軌道を辿りすれ違う星同士のように、すれ違った瞬間に、実は次にすれ違うまでの最も大きな距離を抱えているのだ。
僕は、今でもあの日の沙希との距離以上に遠い場所を知らない。
Ⅸ

深夜のコンビニでの買出しを終え、僕はスマホをいじりながら家へ向かう。
仕事がひと段落した僕は、春から夏へ、季節の変わり目の空気を感じたくて、わざとのろのろと歩く。
少し向こうで信号が点滅をはじめ、やがて赤に変わる。
立ち止まると、僕はビニール袋をプラプラと揺らしながら、懐かしい歌を口ずさんでみる。
車は1台も通らず、風は絶えていた。
盛大なあくびで伸びをして、僕はスマホから向かいの信号に目を移す。
もう一組の僕たちは、今も横断歩道の両側で信号が変わるのを待っている。
永遠の揺りかごの中で、何度でも僕はそれを渡るのだろう。
信号が点滅を始める。
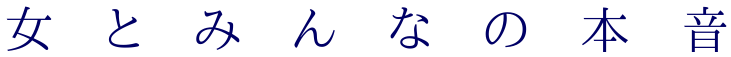
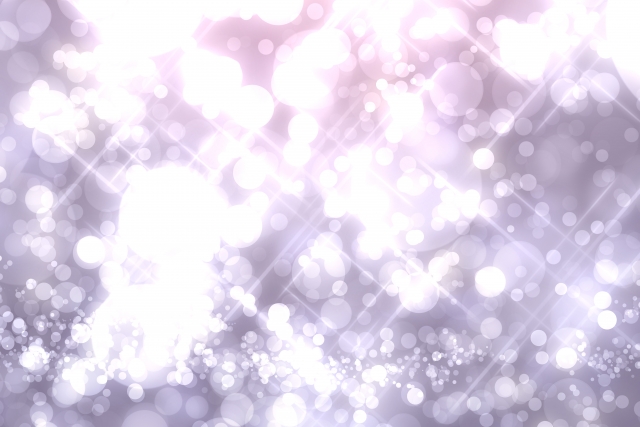



















コメントを残す